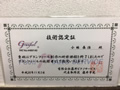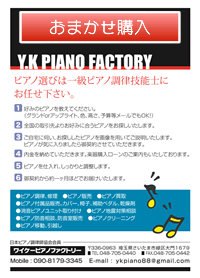1. お子さまの才能、そのピアノに殺されてませんか。
一発勝負の発表会やコンクールなどで、十分に実力を発揮できなかったというお子さまには、普段アップライトピアノで、一生懸命練習している子が多い。これ事実です。
「え?」と、お思いになる親御さんも多いことでしょう。「どういうこと?」
それは、アップライトピアノとグランドピアノでは、演奏技法(弾き方)が異なるからです。言い換えますと、指の筋肉の使い方が違うのです。
「それじゃ、グランドピアノを買わなくちゃだめだということ?」
そんなことを言うつもりはありません。なぜなら、今あるアップライトピアノをあたかもグランドピアノであるかのような、響きとタッチを実現するピアノの装置――グランフィールが開発されたからです。
グランドピアノは価格が高いだけでなく置き場所もとります。また音量もあるので防音室が必要になるケースも多く、お子さまの習い事としては初期投資が高額過ぎます。
それでは裕福な家庭の子息でなければピアニストにはなれないのか?
いいえ、無限の可能性を孕(はら)むグランフィールを一刻も早くアップライトピアノに取り付け、お子さまの才能がピアノによって殺される前に、グランドピアノに近いタッチに慣れること、それがとても大事なのです。

グランフィールは、アップライト用に開発したレペティションスプリングを既存のジャックストップレールに取りつけることで、鍵盤を3分の1戻すだけで次の音が出せるようになる。
グランフィールを写真で説明するのは、わかりずらいので、ページの最後にビデオによる解説を準備いたしました。よろしければご覧ください。
1.グランドピアノとアップライトピアノのパフォーマンスの違い
グランドピアノとアップライトピアノには、二つの大きな違いがあります。
まず、最初の違いは、連打性能です。同音のトリルでグランドピアノは1秒間に14回打鍵が可能ですが、アップライトピアノでは1秒間に6〜7回とグランドピアノの半分以下の性能です。
そして第二の違いは、鍵盤の操作性です。鍵盤の深さ(鍵盤を押して底に着くまで)は、基本10mmに設定してあります。これはグランドピアノもアップライトピアノも同じです。
しかし次の音を出す(連打する)時に、大きな違いを生じます。アップライトピアノでは鍵盤を元の位置に戻さないと次の音が出せません。つまり、10mm押すことで音が出るわけですが、次の音を出すには、また10mm上に戻して初めて、その準備が整うわけです。
これがグランドピアノでは10mm押して音が出て、3〜4mm戻すだけで、もう次の音が出せるのです。
これにより連打性能も当然高くなるのですが、グランドピアノとアップライトピアノのタッチの違いは、「ピアニッシモの連打」と「レガート奏法での同音連打」という技能面で明確になります。それは、圧倒的な『表現力の違い』となって現れてくるのです。
[補説]
「ピアニシモの連打」という技能は、バッハやモーツアルトに代表される『古典派』の楽曲には見られません。それはフランスのエール社が現在のグランドピアノにも使用されているレペティションスプリングの原型を開発した 1821年まで待たねばなりませんでした。これによりグランドピアノの連打性能が飛躍的に向上すると、ロマン派といわれるベートーベン、ショパン、リスト以降の作曲家の曲を弾くための必須奏法となっていきます。
「レガート奏法」とは、前の音と次の音を途切れなうように弾く奏法です。この時、ダンパーという部品で、弦の震動を止めます。ダンパーは鍵盤を5〜6mm上に戻すと弦の振動を止めるように調整します。
ですが、グランドピアノでは鍵盤を3~4mm上に戻せば次の音が出せるので、ダンパーが弦の振動を止める前に次の音が出せる。つまり、前の音が消える前に次の音を出す。これがレガート奏法での同音連打です。
「ピアニシモの連打」と「レガート奏法での同音連打」という技法は、アップライトピアノで実現することは、きわめて困難です。
2.パフォーマンスの違いから生じる弾き方の違い
アップライトピアノを弾くときは、鍵盤を元の位置まで戻さないと次の音が出せません。鍵盤の底に落とした指を手の甲の筋肉を用いて、最低でも10mmは上に持ち上げることになります。ましてやそれを一曲何千回も繰り返す訳ですから、知らぬ間に無意味な筋力の消耗や少なからず手先への負担が発生しています。
その点グランドピアノは鍵盤を3〜4mm戻すことで次の音を出します。しかも鍵盤の底に落とした指の力をゆるめるだけで、自然に指が上にあげられるのです。
「レペティションスプリング」による反動のおかげです。
ですからグランドピアノでは脱力を身につけることが、レベルアップにつながります。しかしアップライトピアノではこの脱力奏法はできません。アップライトピアノでグランドピアノの脱力奏法をおこなうと、音が抜けてしまい、音が出ないこともあります。
3.弾き方の違いがもたらす子供さんが受ける不利益
自宅で一週間、頑張って練習して、上手く弾けるようになっても、先生宅でいざレッスンするとなかなか上手く弾けない。
こんな経験はどなたにもあることと思います。もちろん緊張することも原因の一つでしょうが、それだけでないことは、すでにご理解のことでしょう。
そうです。アップライトピアノでいくら頑張って練習しても、グランドピアノとはそもそも弾き方が違うので上手くいきません。先生宅でグランドピアノに慣れるのに時間がかかり、レッスンが終わる頃になってやっと慣れてくる。その繰り返しでレッスンにも無駄な時間を要することになってしまうのです。
一発勝負の発表会やコンクールなど尚更です。実態はピアノに慣れる時間もないままに終わってしまった、ということでしょうか。
4.グランドピアノの響きとタッチを簡単にアップライトピアノに
西暦1800年に発明されてから200年以上経過したアップライトピアノ。これは世界中のピアノ製作者や調律師がグランドピアノに近づけようと、試行錯誤してきた200年とも言えます。
フランスのエラール社は1821年、グランドピアノに「レペティションスプリング」を付けた大発明をし、現代のグランドピアノにも使用されています。グランフィールは言い換えればこの「レペティションスプリング」をアップライトピアノ用に開発したもので、200年以上続く先人たちの想いを形にした21世紀の大発明であると、私は断言いたします。
また取り付けが簡単なのも素晴らしい。お持ちのアップライトピアノのアクションに数点の部品を加えて調整するだけです。
工期はわずか2、3日です。取り付けたことによるデメリットは一切ありません。それどころか響きもアップします。これはハンマーが弦に接触する時間が、グランドピアノ並みに早くなるため、高次倍音が消されないからです。消音機と一緒に取り付けることもできます。
習い始めのお子さまには、少しでも早くグランフィールを取り付けてグランドピアノタッチに慣れさせてあげてください。
またピアノを趣味で習っている大人の方々は、アップライトピアノだからと言って諦めていた表現が、グランドピアノ並みに実現できるようになります。
ビデオによるご説明
ビデオ1
アップライトピアノにグランフィールをつけると、どのようにかわるのか?
ハンマーの動きにご注目ください。
ビデオ2
グランドピアノのハンマーの動きをアップライトピアノで実現~連打性能をアップライトピアノに付与したグランフィール技術です。
ピアニストの感想~ Y.K PIANO FACTORY ピアノ講師 馬渕瞳
グランフィールを初めて弾いたときの衝撃は忘れられません。アップライトピアノなのに!? と驚くばかり…
特に驚いたのが、アップライトピアノでトリル(2本の指で2つの鍵盤を交互に弾く奏法)を細かく入れようとしても鍵盤が戻って来ないのに、グランフィールだと鍵盤が戻ってくる!どんなに指を早く動かしたって、鍵盤が戻って来なければ音にはならない。そうした技術面での違いがあります。
また、アップライトピアノではなかなかp(ピアノ)やpp(ピアニッシモ)の音を出せないのに対して、グランフィールは出せる!ということ。なんとなく頭ではこんなpの音を出そうと想像して、指のタッチをコントロールして弾くものの、いざ打鍵するとあれ? pの音が出ない。ということがアップライトではあったのに、グランフィールではそれがないんです!
強弱というのは音楽を表現する中で、絶対に必要なもの。強弱が出来れば表現力もupです!まだまだグランフィールの良いところはありますが、要するにグランフィールは凄い!
グランドピアノに近いタッチと表現が出来るのです。発表会やコンクールでは必ずグランドピアノを使用します。
お家のアップライトピアノで練習して、いざ本番グランドピアノを触ると、戸惑う生徒さんたちがいらっしゃいますが、それは当然。
そしてその戸惑いが本番の演奏に影響するということもしばしば……。しかし、練習と本番のピアノの差を縮めておけば、戸惑わず練習でできていた通りの演奏ができるはずです。
それもグランフィールの強みだと思います。
グランフィール:よくあるご質問
- グランフィールの価格を教えてください。
グランフィールの価格は、部品代と取り付け工事費込みで、税抜¥200,000です。ただし、ピアノの状態によっては、取り付け前に部品交換や整調が必要となる場合があります。ピアノ本体の修理、調整及び部品の交換等につきましては別途実費(お見積り)となります。
- グランフィールを取り付けるのに、どのくらいの時間が掛かりますか?
取り付け時間は丸3日かかります。お客さま宅のピアノに取り付けるには、1日目の朝イチで伺いアクションを引き取り工房で作業となります。2日目、工房で作業。3日目にお客さま宅で装着後のアクションをピアノに戻し微調整します。ピアノの大きさ、高さで難易度の違いはさほどありませんが、ピアノの状態によってはグランフィールを取り付けるまえに部品の交換や整調の必要があります。
- 取り付けたグランフィールは、外から見てわかりますか?
全く分かりません。ピアノの内部、それも暗い部品の間を覗き込まなければ見えません。みなさんに、わかりやすくご説明するために、ビデオを作成したほどです。
- グランフィールをとりつけることで、デメリットがあったら教えて下さい。
取り付けたことによるデメリットは一切ありません。それどころか響きもアップします。これはハンマーが弦に接触する時間が、グランドピアノ並みに早くなるため、高次倍音が消されないからです。また、消音機と一緒に取り付けることもできます。